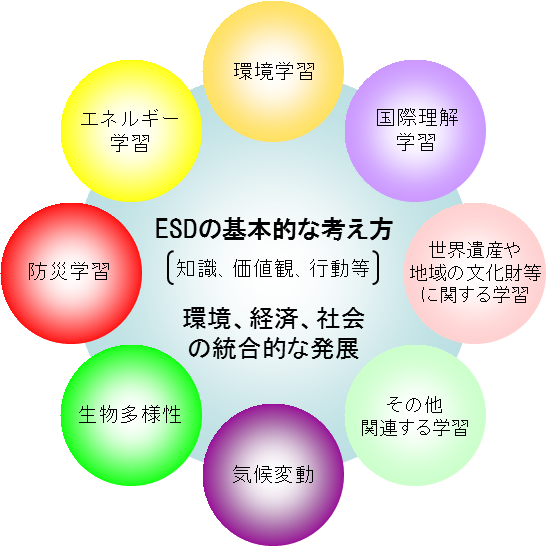![]()
現在フェイスブック上のイベントとして、「使っていない知育玩具をネパールの公立学校にプレゼントしませんか?」という呼びかけをしています。イベントの詳細はこちらのイベントページをご覧ください。
このたび、ネパールのチトワンの公立小学校を支援している現地NGO( https://www.eccnepal.org/ )スタッフの要請で知育玩具を集めることになりました。皆さんのご家庭に眠っている、現在使っていない知育玩具を譲っていただけませんでしょうか?
●どこに送ればいいの?
大阪淀川区十三の「ゆるらかふぇ」に集めて、一箱23㎏以内に梱包し、8月21日必着で羽田空港に送ります。スンダリ国際支援連絡会議の代表として、スンダリミカがネパールまで運び、NGO関係者に手渡しします。
![ããã³ãã¼ã«ç®±ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
送付先
〒532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目18−18
ゆるらかふぇ
電話: 06-7493-9719
※送付する前に、こちらのブログのコメント欄かイベントページかゆるらかふぇまで必ずご連絡ください。事前に連絡なしで荷物だけ送るのはご遠慮ください。
※ゆるらかふぇまでの送料は各自ご負担くださるか、直接持ち込んでください。着払いでの発送はご遠慮ください。
●どんなものが欲しいの?
【お家にこんなものありませんか?】
●英語の知育玩具(※ひらがなカタカナは募集していません)※写真はイメージです。
![ãè±èªãç¥è²ç©å
·ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
●算数の知育玩具(※小学校で使う算数セットは今回は募集しません→前回募集して現在数は足りているので)※写真はイメージです。
![ãç®æ°ãç¥è²ç©å
·ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
●積み木やレゴブロック(※比較的小さなもの)※写真はイメージです
![ãç©ã¿æ¨ ããºã« ç¥è²ç©å
·ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
●パペット(※手作り品でもよいです。)※写真はイメージです。
![ããããã ç¥è²ç©å
·ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
●カードゲーム(※トランプ以外のもので。UNOとか)※写真はイメージです。
![ãã«ã¼ãã²ã¼ã ç¥è²ç©å
·ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
※こんなものは送らないでね。
【こういうものはご遠慮ください】
●日本語の教育に関するもの(※使うのはネパール人の子供です)
●著しく欠品しているもの(※使用に支障が出るほどの著しい欠品)
●不衛生なもの(※異臭を放ったり、カビだらけのもの)
●電池や電源を必要とするもの(※使用に維持費がかかるモノ)
●重すぎる・大きすぎる・かさばりすぎるもの(※手荷物で運びますので)
●文房具(鉛筆やノート)は今回募集していません。※文具を現地で購入する費用としての寄付は歓迎しています。
●お金を送って協力することはできるの?
少額クラウドファウンディングサイト POLCAを通じて寄付が出来ます。
https://polca.jp/projects/tRiM4JsOvMg
![]()
スンダリ国際支援連絡会議のボランティア用ゆうちょ銀行口座でも寄付を受け付けてます。
寄付金専用 ゆうちょ銀行 10200-99109761 タカギミカ
※1000円以上の寄付をしてくれた方で、リターンギフト(ラクマとメルカリに出品中のもの)をご希望の方は、振り込み証明書の写真といっしょに、郵送希望先住所・希望商品をこちらのメールアドレスまでお伝えください。
メールアドレス: sundarimusic.info1アットマークgmail.com(アットマークを@にしてください。)
●小さな贈り物がもらえて寄付もできるチャリティーギフトショップもあります。
寄付のリターンとして、カレースパイスやフェルトマスコットなどがもらえるギフトセットです。現在9点が出品してあります。1000円の購入金額のうち半額の500円をネパール支援にあてます。※Sold Outになっても、すぐに購入できるように商品を出品しますのでお好きなものをお求めください。アプリに登録してある住所とは違う住所に郵送することもできます。取引メッセージにてご希望をお伝えください。お友達と、ネパールの子供に同時に贈り物が出来るギフトセットです。
楽天のフリマサイト ラクマ
https://fril.jp/shop/SILCSHOP
![]()
![]()
メルカリショップ※ラクマと同じものを出品しています。
https://www.mercari.com/jp/u/770529634/
![]()
今回支援をすることになった背景をご説明します。
●チトワンの学校ってどこにあるの?
チトワンというのはカトマンズから西に100㎞程離れた場所ですが、この地域にはタルー族という民族がたくさん住んでいます。タルー族は一般に貧しく、教育を受けていない人たちが多いといわれています。![ãå°å³ãããã¯ã³ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ]()
この地にある公立学校の立て直しプロジェクトの責任者となったのが、スンダリミカの古くからの友人のサファラ先生で、彼女は先生を指導する先生という職業をしています。サファラ先生とは何度かネパールでプロジェクトをご一緒したことがあります。
ドキュメンタリーフィルムWASTE MANDALA をご紹介した時のブログのトップ写真にも映り込んでいた人ですが、見おぼえありませんか?
https://ameblo.jp/sundarimica/entry-12333674965.html
![]()
●サファラ先生ってどんな人なの?
サファラ先生は質の高い教育をネパールの公立学校に届けたい、という思いで教員の指導をされている方です。サファラ先生が提唱する質の高い教育を子供たちへの思いをつづったレポートはこちらです。2014年くらいに発表されたレポートですが、現在も状況はあまり変わっていません。
![ç»åã«å«ã¾ãã¦ããå¯è½æ§ããããã®:1人ã座ã£ã¦ã]()
※自ら知育玩具教材を作るサファラ先生
==========================
ネパールの学校教育に関する報告: 今、子どもたちが必要としていること
概要
昨今、ネパールの遠隔地であっても、子どもたちのほとんどが学校に在籍しています。ユネスコによる“万人のための教育”プログラムは、たとえ政府による公教育制度の質が悪いと言っても、ほとんどの子どもたちが学校教育を受けるのに役立ちました。ほとんどの学校では、適切な教室、トイレ、飲料水など最低限の設備さえも欠けている状態ですが、公教育制度は無料ですから、子どもを私立学校に通わせる余裕のない家庭にとっては、公立学校が唯一の選択肢なのです。
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
どの公立学校でも男子生徒より女子生徒のほうが若干多いという現象が見られますが、両親が男の子は私立学校へ行かせ、女の子は公立小学校の5年生までの教育で充分と考えているからなのです。一般的には、私立学校志向が強く、日本をはじめ外国援助を受けて建設された村の公立学校が廃校になりつつあります。しかし、そうした中でも、本当に貧しい階層の多い地域では、公立学校しか教育の機会が得られません。教育の二極化現象が起きているのです。現在では、10年間の学校教育を受け、卒業資格試験(SLC)に合格していなければ、まともな賃金を得ることも、海外への出稼ぎにも行くことも難しいので、この子どもたちの将来は既に限定されてしまっているのです。
貧しさは、地方にあるとは限りません。カトマンズ盆地の周辺でさえも、支援を必要としている地域があります。もし、支援が得られれば、貧しい子どもたちの能力開発教育を施すことができるのです。
最終目標
★教育を必要としている子どもたちのために、質の高い教育を提供すること
★国のために役に立つ善良な市民を育成すること
【教育の質的向上を図るためのビジョン】
見定め:教材等の導入状況など、標準基準を用いて、最も支援を必要としている学校を確実に見定めること。
計 画:彼らの必要性や優先順位を明確化するために、校内を点検し、校長、教師とスタッフたちとの会議を開催すること。
活 動:学校の校長、教師、スタッフたちと共に、活動改善計画を作成すること。
【目的: 教育の質を向上させるための方策】
1. 新しい教材を与える。
2. 教師研修会で与えられる新しい教授法を導入する。
3. 全人的な経験を与えることで、心理的・社会的、物理的および感情的な成長を図る
4. 両親に教育を与える
5. ボランティアを参加させる
------------------------------------
1.新しい教材を与える
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
政府の学校では、教材が不足しています。教材といえば、黒板と数本のチョークのみです。こんなことは、驚くに足りないことで、文房具類、画用紙、クレヨン、絵カード、図表、辞書、地図、読書用図書、ベース10グロック(加算、減算、数感覚など基本的な数学的概念を学ぶための教材)、立体模型、コミュニティ・モデル・ボール、綱など、あらゆる教材がありません。
これらの教材は、子どもの様々な能力を開発することができます。子どもたちは、こうした教材を使って、ものごとを探ってみたり、創ったり、感じたり、遊んだり、対話を始めるのです。
アイデアやインスピレーションは、多くの場合、西洋の例が用いられますが、いつも、それらをネパールの文脈に合わせて利用します。これらの教材を用いると、子どもたちの普通の認知能力よりも、探究心、創作意欲、想像力、感受性、人間関係構築などの能力開発において、はるかに高い効果が得られるのです。学習が彼らにとって総合的な経験になります。
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
2.新しい教授法の導入
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
ネパールに、僅かながら教師研修センターがあります。政府は、教師に研修の機会を与えていますが、学校においてはその顕著な効果は見られません。ほとんどの教師は、伝統的な暗記学習教授法を踏襲しています。教師は教科書を読み、子供たちは単に暗誦するだけです。教師が50年前に受けた教育法を繰り返しているだけです。その結果、できない子は心を悩まし、教師は、竹の棒で子どもを叩きます。
今までの伝統的な教授法を、子どもの総合的な開発のための新たな教授法に置き換えることは可能です。私たちは、必要な設備を整備して、子どもと教師の間の良好な関係を見出し、子どもに優しい環境をつくることに無関心でいてはならないのです。多種多様なツール(劇をしたり、一緒に歌ったり、ペアやグループで絵画の発表をしたり)を使った教育は、子を中心とした学習指導の重要な部分であり、そうしたゲームや教材を開発する必要があります。
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
教育フェアをするのも、一つの方策です。教師研修内容は、上記に示した内容を基準として充実したものになるでしょう。もっと多くの教師が研修してきたことを生徒と一緒になって実践すれば、もっと多くの生徒が能力を伸ばせるでしょう。
子供たちが、教室で何を学んだかを発表する教育発表会は、もう一つの教育ツールです。発表会を行うことで、新しい教育方法がいかに有効かを示し、理解することができます。
3. 総合的な経験教育 (認識能力、社会的、物理的、心理的成長)
認識能力の成長(例えば、単に習慣を形成するものではなく、積極的な知力のを含む過程で、ものごとの規則を自分で見つけるなど)、社会的な成長、物理的な成長、感情や心理的な成長などを促す総合的な経験教育を与えることが必要です。
学校で、必要なツールを与え、活動の場や材料を提供することで、総合的な経験を与え、子どもたちの知的なスキルだけでなく、社会的スキルや物理的、感情的なスキルなどの開発を支援することができます。
感情的な領域の開発には、日本の教育から学んだ、子どもたち個別に鉢を与え、それぞれが好きな植物を植えて慈しみながら育てるというアイデアを実施してみようと考えています。
![]()
※チトワンの学校をサファラ先生が視察した時のレポートより
4. 両親の教育機会提供
5. ボランティア受け入れ促進
もし可能なら、教育現場にボランティアが存在することで、子どもが何等かの影響を受け、教育にも効果がもたらされるでしょう。ボランティアは、村内で最低限の設備や生活環境で暮らせる能力があり、明るく、忍耐強く、創造性があり、英語かネパール語が話せる人が望ましい。
ケーススタディとして:カファルチョールのセティ・デヴィ小学校訪問記
セティ・デヴィ小学校はカトマンズから15km離れたノウビセのカフレチョールにあります。この小学校からは、ヒマラヤの峰々がとても良く見えます。
彼らは、たいへん協力的でしたが、ほとんどが貧しいタマン族の人々でした。そのことが、ここの学校教育を困難にしている原因なのです。生徒は全部で110人で、ECDクラス(幼稚クラス)が1クラスと、他は1年生から5年生までの6クラスあり、7人の先生が教えていました。
観 察
- 専任教師-- 殆どの教師は険しい山を1時間程度歩いて登校してきますが、それが普通です。
- 訓練を受けた教師は、新しい指導法を使用しています。
- 学校の設備は充足していました。
- 図書館は利用されていました。
- 数人の教師は教材を使っていました。
課 題
- 境界柵が無い:学校の設備は整っているが、学校の境界柵が無い。校長先生の話によると、境界柵を設けると、子どもたちが昼食後学校から逃げ出さなくなるだろうとのことだった。
- お弁当が無い:ほとんどが貧困家庭の子どもたちのため、充分な食事が得られない。校長先生は、もし昼食の援助が得られれば、子どもたちは学校に留まり、1日中勉強することができるだろうと語った。
- 教材不足
- 教師の教育訓練不足
- 生徒たちの創造性の無さ
- 図書館の適切な利用不足
- 両親の教育不足と貧困
- 低賃金の教師(★正規の政府雇いは平均的に教師の半数程度で、他は村雇いのため低賃金である)
支援のお願い
- 教育研修を提供すること: 教育研修は教師に子供本位の環境と教授法のインパクトに関する知識を与えることができる。同時に、教師たちは、子どもの総合的な能力開発に関する知識も得ることができる。つまり、教員研修の機会を与えることで、教師と生徒の教育に対する考え方を同時に正すことができるのです。
- 昼食の提供: 質の高い教育が必要なことは分っています。しかし、基本的なニーズが満たされない限り、夢を見ることは不可能なのです。子供たちに昼食を提供できれば、子どもたちに規則的な生活習慣を身につけさせ、学習させることが可能となり、子どもたちにとっても、両親にとっても、教師にとっても大きなサポートになります。
- 学校の境界柵を作ること: 食が満たされれば、衛生、安全などが、子どもたちの基本的なニーズになります。学校の境界柵(塀)を築けば、子どもたちが勝手にいなくなるようなことがなくなり、学校の中で安全に滞在することができます。
- 教材を提供すること: 教材が提供されれば、教師も子供たちも、通常の認知能力よりも遥かに創造的になり、総合的な人格開発に資することができます。
- 植木鉢を置くこと: 生徒が一人一人、自分の責任で植物の鉢を世話することは、子どもの感情的な部分の成長を助けます。この計画案は、日本の小学校教育システムを応用したものです。
- ボランティアを提供すること: 学校でのボランティア(または、インターンシップ)の機会を提供することは、ボランティアにも、子どもたちにも、新しいアイデアを探求する機会を与えることになります。ボランティア側は、彼らはネパールとネパールの状況を知るチャンスとなり、子どもたちは彼らの世界を探求する機会となります。これは、ボランティアが、子どもの生活に、今までとは異なる「何か」を生みだすことを意味します。
貧しい状況にある子供たちも、平等な教育を受ける権利を持っています。
ネパールの子どもたちを支援 し、彼らの人生を変えようと思ってくださる方を
歓迎いたします。
Safala Maiya Rajbhandari 記 2014年
(*ラトバンガラ教育財団 教員研修所専属トレーナー)
=============================-
このチトワンの学校サポートプロジェクトではいくつかのサポーターが協力し合って資金や物資の提供をしています。
今期は8月19日まで募集しています。お心当たり、お志、お待ちしています。(((o(*゚▽゚*)o)))